大好評の板ばさみ相談室が、ついに音声コンテンツになって登場!
移動中やお昼休みなどに、ぜひお聴きください。
中間管理職板ばさみ相談室
板挟みの悩み多き中間管理職。あなたの悩みが、みんなのヒントに!?
1000人規模の自衛隊の元指揮官、大企業の顧問を長年経験した組織運営のベテランが、
あなたのお仕事の悩みにお答えします。
Q44
マイクロマネジメントにうんざり
- 2025-02-17
- 営業部 部長(40代)
営業部の部長を務めています。現在、元営業本部長である執行役員が、営業部の業務に対して細かく口を出してくる状況に困っています。執行役員は自身が部長だった頃のやり方や成功体験をそのまま押し付けてきますが、現場の状況や市場環境が大きく変化しているため、そのやり方が必ずしも今の業務に適しているわけではありません。加えて、細かい指示や提案は時にピントがずれており、部下たちも混乱しています。執行役員自身は「役員として営業部を支えている」という意識で張り切っているようですが、結果的に現場のモチベーションや効率が下がりつつあります。このような状況下で執行役員と良好な関係を保ちながらも、現場の自立性や効率を維持するためにはどのように対応していくのが良いでしょうか。
A44
コミュニケーションレベルを高めていく努力を
今回も難しい問題ですね。相手が元営業本部長だった執行役員ですから、なかなか思うようには考え方、やり方を変えてもらうことは簡単ではありません。
そこで本質問の解決の糸口を探すために、まず基本に立ち返って、そもそもマイクロマネジメントとはどういうことなのか?その弊害はどういう点にあるのか?何故、元営業本部長である執行役員が営業部の業務に対して口出しをするのか?などを以下、考えてみたいと思います。
- マイクロマネジメントとは?
上司やリーダーが部下の行動を細かく管理し、過干渉して厳しく統制するマネジメント手法です。 - その弊害は?
マイクロマネジメントは、例えば、細かい進捗報告を頻繁に要求したり、仕事の進め方を必要以上に細かく指示したり、その他電話の掛け方までひとつひとつ口出しする、部下の居場所や行動を常に把握しようとするなどです。
その弊害として、部下の自主性を抑え、モチベーションを下げ、優秀な人材が育たず、組織の効率や部下のパフォーマンスに悪影響を与えることが多く、メンタルヘルスへも悪影響及ぼすことがあります。 - マイクロマネジメントをしてしまう理由は?
ひとつは上司自身が「不安」を持っているということです。
不安というのは上司自身、部下が旨くやらないと自分の業績を問われるということ、つまり営業部長以下を信頼できないのです。
もう一つは、上司の「自己顕示欲」です。元営業本部長として俺はこれだけやってきた、営業部のことは何でも知っているという態度です。
マイクロマネジメントはそんなに悪いことなのか?
ということですが、それを考える前にマイクロマネジメントの対義語であるマクロマネジメントについて以下述べたいと思います。
マクロマネジメントとは、「部(チーム)の方向性を示したうえで部下の自主性を重んじて任せることで部下のモチベーションを高めるマネジメント手法」です。部下の人数が増えてくるとひとりひとりに細かく指示を出すのは現実的に不可能なためマクロマネジメントを取り入れるのは自然の流れと言えます。
マクロマネジメントを適切に行うためには以下の点がポイントとなると思います。
- ①会社の基本である理念やビジョンを繰り返し発信して社員に浸透させる。
- ②ゴール(目的、目標、あるいは任務)を明確にして向かうべき道筋を示す。
- ③「何故やるのか」その必要性、重要性を良好なコミュニケーションにより徹底する。
以上マクロマネジメントについて述べましたが、私が以前いた自衛隊でも、指揮の要訣(ポイント)として、①部下の自主積極的な行動 ②部下に対して自主裁量の余地を与えることが重視されていました。これもまさにマクロマネジメントです。
少し脱線しましたが本論に戻ります。それではマイクロマネジメントそのものは悪いことなのかということです。
今まで述べた通り明らかにマイクロマネジメントは弊害が大きいと言えます。しかしながら、組織や部下の成熟度、構成員の仕事に対する慣熟度から考えて、失敗に至る前の転ばぬ先の杖としてのアドバイス、少々の干渉、教育の一環として行なう指導など相手のことを慮る行為は必ずしも弊害ばかりではなく、善意、好意的なものとして受け止める態度も必要となります。
1~3までマイクロマネジメントの基本的なことを述べました。それらを基に本質的な解決の糸口を探って参りましょう。
コミュニケーションレベルを高めていく努力を
元営業本部長である執行役員が細かく口を出してくる現状ですが、「不安」が理由であれば、失敗を避けるために早めの助言のつもりかも知れません。あなたの部が信頼されていない可能性があります。その場合はあなた(部長)及び部員が信頼を獲得しなければなりません。
そのため、次の4点を挙げて参考に供したいと思います。
- 執行役員の不安解消のために日頃の業務を整斉と行い、部の団結力を示していく。地道な努力の継続です。
- 執行役員と良好なコミュニケーションを取る努力をする。報告や指導を受けるなど意識的に会話する場を作っていく。
- 執行役員のすべてが悪い訳ではないと思われるので良いところは素直に受け入れる努力をする。
- 間違い、勘違い、意見の違いなどについては、毅然として意見を述べることも部長としてのあなたの努めです。特に現場の状況、市場環境の変化に伴う業務のやり方やピント外れの指示等については、しっかり意見を述べてください。
次に「自己顕示欲」が理由であれば、上司は「自分が100%正しい」と思っている場合が多く、何かと考え方、やり方など部下を自分と同じように強要しがちです。
この場合が一番困ったことです。本質問の場合は、この「自己顕示欲」が理由ではと思えます。冒頭に難しい質問だと言ったのがこのことです。ではどうすれば良いのでしょうか。
私の基本的考えは「人を変えることはできない。変えたければ自分が変わることです。自分が変われば相手が変わる可能性がある」です。
そこで以下5点を解決の参考にしていただければと思います。
- 執行役員の自尊心を傷つけないように配慮する。大人の対応です。執行役員の全てが間違っているわけではないと思うのです。よって正しいアドバイスには感謝を述べて受け入れることです。
- 意見の違うところは、その理由を明らかにして毅然とした態度で意見(具申)することも重要です。決して感情的にならないことです。
- あなた自身が部長としての責務を果たす。取り入れるべきところは取り入れると共に、この点については私のやり方、考え方に任せて欲しいと明確に伝えることです。
- 自己顕示欲の強い人は人一倍認められたいと言う意識が強いものです。たとえ上司でも人に認められると嬉しい、喜ぶものと心得ることも必要です。ひょっとしたら執行役員の態度が変わるかもしれません。
- やはり良好なコミュニケーションは重要です。決定的な対峙を避けつつ、部長としてのあなたを認めてもらう努力をしてください。
そのためには、コミュニケーションレベルを高めていく努力を怠らないようにしてください。
あえて付言すれば、「コミュニケーションは人生のすべての問題を解決する大きな武器」と心得ましょう。
老婆心ながらここで最も避けなければならないことは、執行役員の過干渉などに対して、態度に表したり、部下と一緒になって悪口、不平不満を言わないことです。
以上、述べて参りましたが、上に立つもの(リーダー)は、部下統率の真髄をマスターすべく、日々勉強、努力をして欲しいものです。と言う私こそまだまだ勉強不足、勉強途上の身ではありますが、浅学非才の身を顧みず意見を述べさせて頂きました。少しでも参考となればこの上ない喜びです。
今回のまとめ
- 上司を変えることは出来ない。自分が変わる努力を!!
- 自尊心を傷つけないように配慮するとともに自分の意見を毅然と述べることも必要!!
- 決定的な対峙を避けて、良好なコミュニケーション作りを!!
板ばさみ相談室では皆さまからのお悩みを募集しております。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
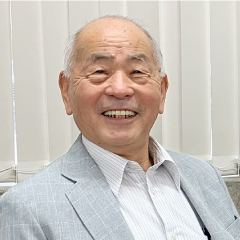
回答者: 呑田好文
元陸上自衛隊レンジャー教官。2002年退官(陸将補)
2018年よりアメリス顧問。2024年2月より同取締役。サロン・ド・アメリス講師。
最近では節分を過ぎ、春の兆しを感じて、水仙、梅、そしてこれから桜、バラと花便りが続くと思い、楽しみにしている今日この頃です。
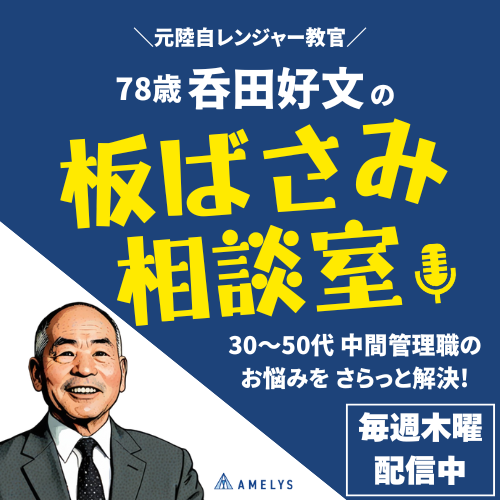

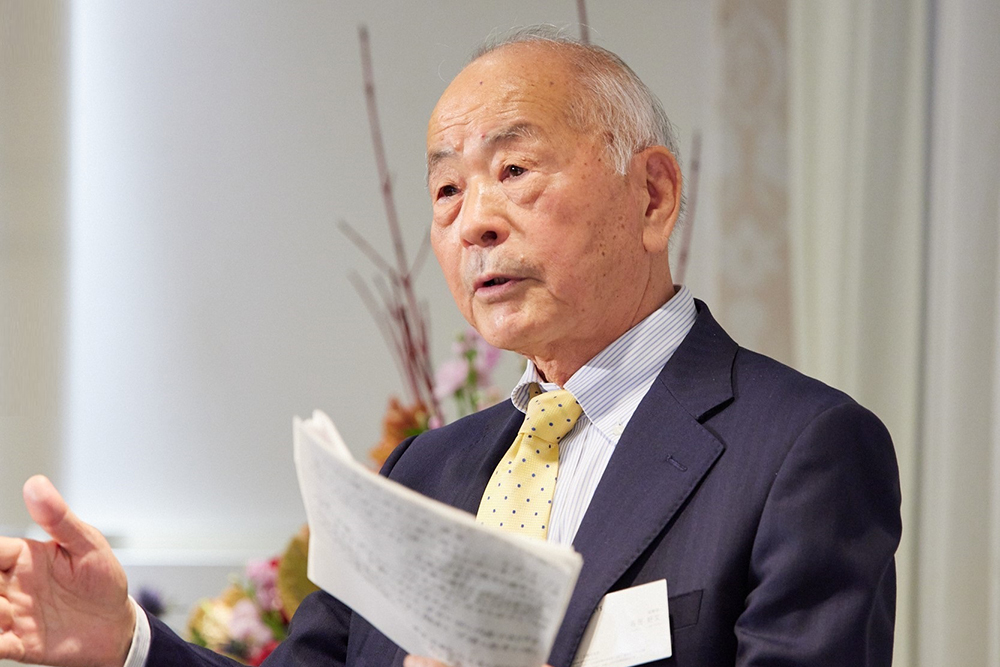
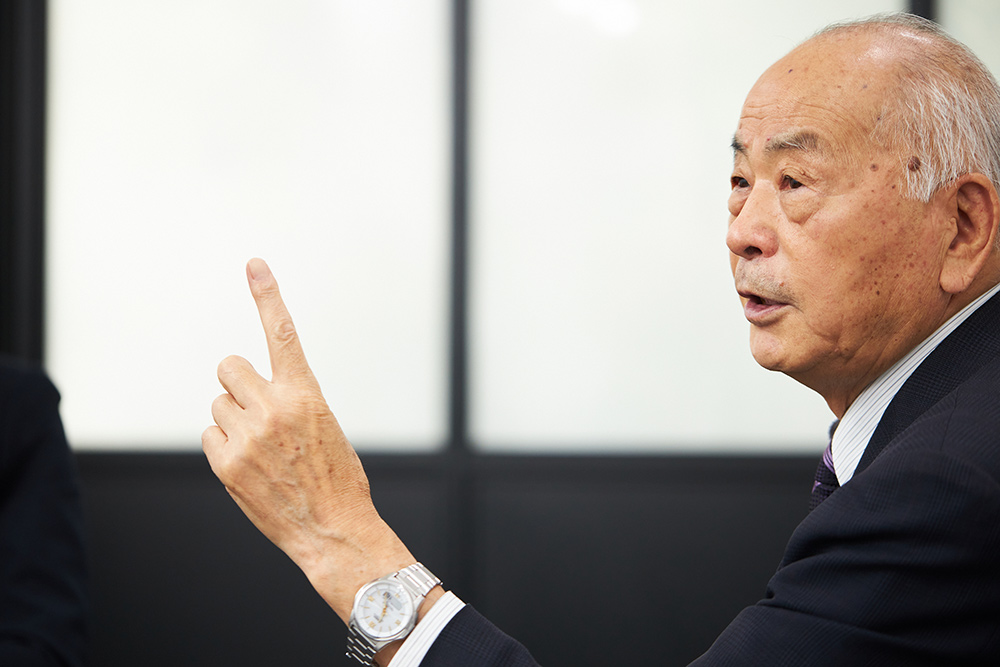
担当者コメント
日頃から上司の考えを理解しようと努め、そのためのコミュニケーションは臆せずとることも重要です。今回のコラムに関連して、こちらの記事もぜひ読んでみてください。