大好評の板ばさみ相談室が、ついに音声コンテンツになって登場!
移動中やお昼休みなどに、ぜひお聴きください。
中間管理職板ばさみ相談室
板挟みの悩み多き中間管理職。あなたの悩みが、みんなのヒントに!?
1000人規模の自衛隊の元指揮官、大企業の顧問を長年経験した組織運営のベテランが、
あなたのお仕事の悩みにお答えします。
Q36
意思決定をひっくり返そうとする人がいます
- 2024-06-24
- 製造業 DX部長(40代)
製造業の会社でDX部長として勤めております。ある営業システムの刷新のプロジェクトについて、長らく方向性を議論していたのですが、ついに社長が決断し、正式に我が部が上申したA案にて進めることになりました。
営業システムの話なので、営業部と具体的にプロジェクトを推進しようと動いていますが、今ここで躓いています。現場寄りの営業部長は前々からその方向性について反対しており、建設的に議論が進まないのです。それどころか、営業部の担当者から話を聞くところによるとB案の方向性にひっくり返そうと色々画策しているようです。
私の営業部長に対する根回しが足りなかった点については反省すべきではあるのですが、私としてはトップが決断した訳なので、あとは実行するのみ、と考えます。営業部長は頑固で年上ということもあり、説得したところで納得するとも思えません。会社としての意思決定が下ったにも関わらず、このスムーズに進まない状況をどう打破したらよいのでしょうか。そもそも会社の意思決定とはどうあるべきなのか、教えてください。
A36
意思決定のプロセスを理解する
本質問は営業システムの刷新プロジェクトなので、社長が決断した背景には、営業部長もその意思決定に参画していたのでは、と思いますが、営業部長抜きでA案にて進めることを決めたのでしょうか。質問だけでは分からない部分もありますが、以下、意思決定の基本的な在り方、手順についてまず述べたいと思います。本質問では、意思決定の基本のプロセスを踏んでいない、あるいは基本が理解されていないことが問題のようです。
「営業システムの刷新プロジェクトの方向性の検討」の手順
- 会社を取り巻く経営環境を分析する。
- 1)社会環境及びその将来のすう勢など
- 2)我が社の経営方針、事業計画の再確認
- 3)我が社の現在の能力、体質の分析検討
- 4)その他
- 会社の目標達成のため、そのプロジェクトの重要性、必要性および実施可否の検討を行う。
- プロジェクト実施の場合の方向性の検討を行う。(本質問ではA案、B案の選択肢があるのでしょうか)
- A案、B案、あるいはC案(あれば)の方向性についてその利害得失(実施する場合の利点・欠点)の分析検討を行う。
- 各案の利点・欠点が明らかになったところで、A案、B案、C案の実行の可能度、処置すべき事項を導き出し、比較検討する。
- そして、最良の案を決定し、社長の決断を仰ぐ。(この過程において、スタッフである各関係部長はその意思決定に参画しているのが前提です)
プロジェクトにより精粗はありますが、以上のような思考過程の手順を踏んでいれば、本質問のような営業部長は現れないと思います。そうすることにより関係各部が一丸となって営業システムの刷新プロジェクトを推し進めることが出来るものと思います。
次に、以上を踏まえて、本題の会社としての意思決定の在り方について述べたいと思います。
意思決定は、意思決定におけるプロセスをきちんと踏んで最終決定(トップの決心)に至ることが基本です。よって軽々しく変更するものではありません。その決定は、全社を挙げて達成すべきもので、つまり、努力の指向を関係者(あるいは社員全員)に示すものです。
この基本に則り、決定事項の達成に全力を尽くすのが組織のあるべき姿です。
ところが本質問にあるようなこと(決心、決定事項に従わない等)が現実には起こりえます。その場合には、決定事項に対してどうすれば良いのかという問題がありますね。
そこで、次の基本原則も理解してほしいと思います。それは、以下の状況が生じた時にはたとえトップが決心したことでも再検討しなければならないということです。
- 社会環境等、予期しないことが発生した場合
- 経営方針について大きな変更をせざるを得ない状況が生起した場合(人的、物的策源の減少など)
トップの決定事項は、その影響も大きいので、みだりに変更してはいけませんが、上記のような予期しがたい自体が生じた場合、トップは遅疑逡巡することなく勇気を持って変更する決断が必要なこともあります。これも立派な意思決定です。トップには意思の堅固と柔軟性のバランスが求められます。
前々からその方向性について、営業部長が反対していたのであれば、何故、社長決断前の検討段階で反対意見を述べなかったのか。何故別の案(B案)の意見具申をしなかったのか、疑問が残ります。意思決定のプロセスが確立されていないのか、トップの決断後も堂々と反対が許される会社風土であるのかも疑問です。
社長のスタッフとしての部長は、意思決定段階で意見を述べることができる立場にあります。意思決定後であっても意見具申はできます。
これについては、私の板ばさみ相談室の番外編、補佐道のコラムを見て頂きたいと思います。勿論意見具申をしてもトップが異なる決心をした場合、補佐者としての営業部長は、虚心坦懐、全力をもってその決心に従い、そのプロジェクトの成功に尽力しなければならないことは言うまでもありません。
随分前に朝令暮改という言葉が流行ったことがありますが、これは意思決定のスピードと従業員が柔軟に決定に従うことを目指すものでもありました。朝令暮改そのものを推奨しているものではありませんが、トップの決心に潔く従うことは重要なことです。
本題の場合は、社長決断に至る過程において営業部長の意見を取り入れているのか(根回しを十分したのか)が気になるところです。なお、営業部長は年上、とありますが、組織においては、年齢はあまり関係ないと考えましょう。
以上、会社の意思決定に至る思考過程と意思決定の考え方について述べました。意思決定の詳細については、また別の機会にお話しできればと思います。
今回のまとめ
- 意思決定は、プロセスを踏んで最終決定(トップの決心)に至ることが基本であり、軽々しく変更するものではない。
- トップが自分の意見具申と異なる決心をした場合、補佐者はその決心に従い、虚心坦懐、目的達成のために尽力しなければならない。
- トップには意思の堅固と柔軟性のバランスが求められる。
板ばさみ相談室では皆さまからのお悩みを募集しております。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
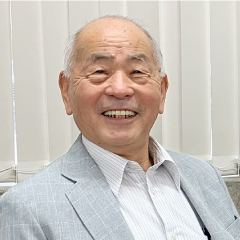
回答者: 呑田好文
元陸上自衛隊レンジャー教官。2002年退官(陸将補)
2018年よりアメリス顧問。2024年2月より同取締役。サロン・ド・アメリス講師。
紫陽花・菖蒲が綺麗な季節ですね。季節の花を愛でるため、休日には色々な所に出掛けています。
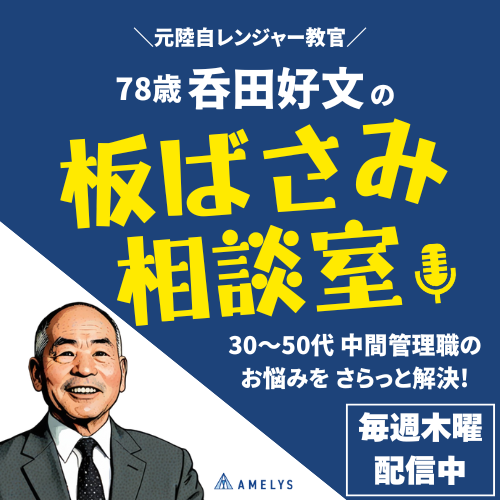
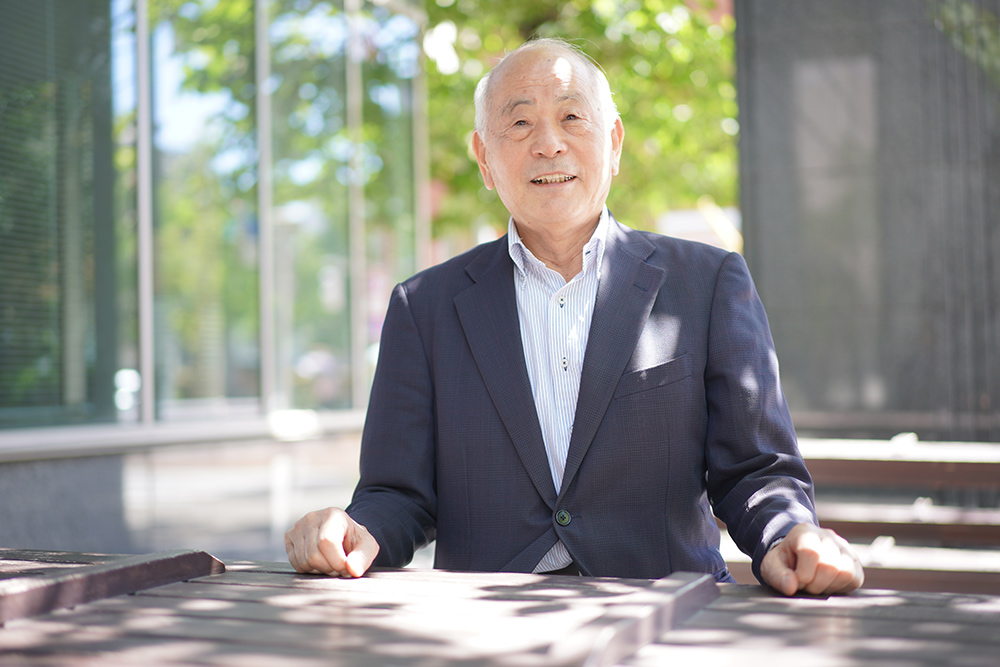

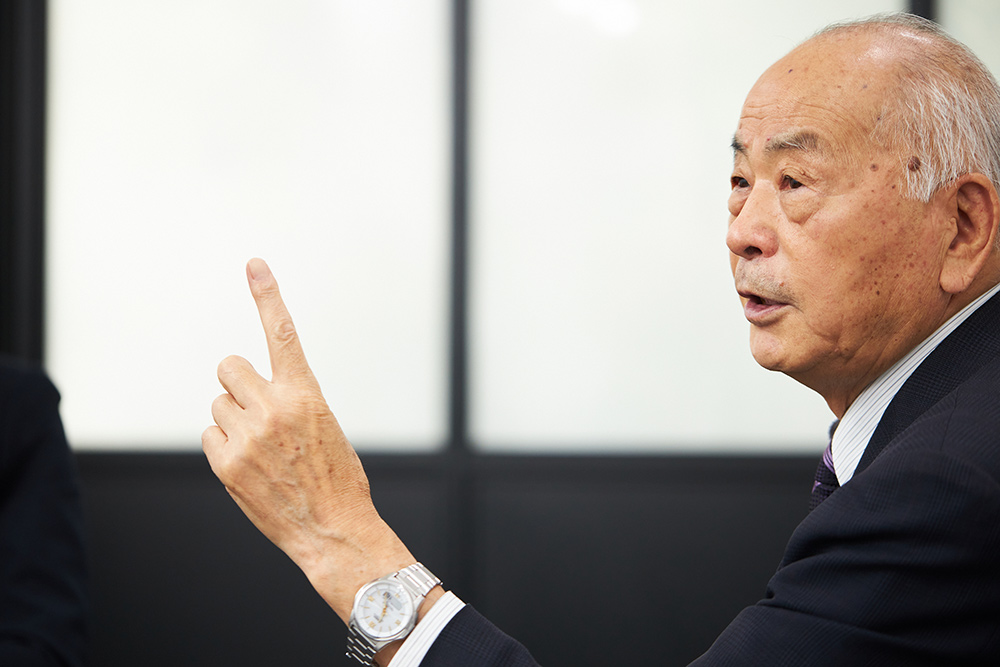
担当者コメント
「意思決定」は組織活動の基本です。
組織活動に欠かせない「補佐道」「指揮道」のコラムも読んでみてください。